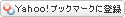特定居住用宅地事例
判断を誤りやすい事例 特定居住用宅地
事例① 居住用宅地が2以上ある場合
相談内容:
1)被相続人の所有する宅地が二つあり、二つとも被相続人が自己の居住用に使用している場合、これらの土地についての小規模宅地の特例はどのようになるか。
2)被相続人の所有する宅地が二つあり、一つは被相続人が自己の居住用に使用し、他の一つは被相続人と生計を一にする親族の居住用に使用している場合、これらの土地についての小規模宅地の特例はどのようになるか。
回答:
平成22年度改正で、被相続人の居住用宅地が2以上ある場合は、そのうち主として居住の用に供されていた一の宅地のみに特例が適用されることとなった。(措置法施行令第40条の2第6項第1号、第2号)
但し、上記(2)の場合のように、被相続人の居住用と生計を一にする親族の居住用の2か所ある場合は、それぞれに特例が適用される。(措置法施行令第40条の2第6項第3号)
事例② 居住用建物が法人所有である場合
相談内容:
被相続人は、その所有する宅地を同人が主宰する同族会社に貸付け、同社はその宅地上に建物を建て、所有していた。
被相続人はその建物の全部を借受け、居住の用に供していたが、この宅地は相続人の居住用宅地として小規模宅地等の特例の対象となるか。
回答:
措置法通達69の4-7は、「被相続人等の居住の用に供されていた建物」とは、被相続人又は被相続人の親族が所有していた建物の敷地の用に供されていた宅地等をいうと規定している。この場合の親族は生計を一にしているか否かを問わない。
上記の場合は、建物の所有者が被相続人でも被相続人の親族のいずれでもないため、土地の貸借または建物の貸借が有償か無償かに関わらず、特例の対象となる居住用宅地には該当しない。
但し、被相続人の同族会社に対する土地の貸付が、相当の対価を得て継続的に行われていた場合において、貸付事業用宅地等の要件を満たせば、特例の対象となる。
事例③ 兄弟二人の相続
相談内容:
被相続人はAとBの二つの宅地を所有していた。
A宅地には自分の家を建てて住み、B宅地は長男に無償で貸し長男はその宅地に自分の家を建てて住んでいた。(被相続人と長男は生計を一にしていた。)
次男は別生計で借家住まいをしていた。
配偶者は既に亡くなっている。
この二人の兄弟がA、Bの宅地を相続するとして、小規模宅地の特例の適用関係はどうか。
- 長男がA宅地を相続した場合
- 長男がB宅地を相続した場合
- 次男がA宅地を相続した場合
- 次男がB宅地を相続した場合
回答:
被相続人の居住用宅地を配偶者が取得した場合は、無条件で「特定居住用宅地」に該当し、小規模宅地等の特例の適用があるが、それ以外の親族が取得した場合は、次のいずれかに該当しないと特例は適用されない。
イ)被相続人と同居していた親族
ロ)相続前3年間借家住まいの非同居親族
ハ)被相続人と生計を一にしていた親族
これらはいずれも申告期限まで所有と居住を継続することが要件となっている。
上記の事例で整理すると次のように判定できる。
| 取得者・宅地 | (イ)同居親族 | (ロ)借家住い3年 | (ハ)生計一親族 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 長男がA宅地を取得 | × | × | × | 減額なし |
| 長男がB宅地を取得 | × | × | ○ | 80%減額 |
| 次男がA宅地を取得 | × | ○(注1) | × | 80%減額 |
| 次男がB宅地を取得 | × | ×(注2) | × | 減額なし |
注1:被相続人の配偶者及び同居の法定相続人がいない場合に限り、要件該当。
注2:B宅地は被相続人の居住の用に供されていたものでないため、要件に該当しない。
事例④ 共同住宅の場合の同居の判定
相談内容:
被相続人は分譲マンションの5階に一室を所有し、配偶者と共に住んでいた。長男は両親を世話するため、同じ階の第三者所有のマンションの一室を賃借して住んでいた。
相続により被相続人のマンションの一室を長男が相続した。
この場合の敷地部分について、長男は被相続人の同居の親族として、小規模宅地の特例を受けることができるか。
回答:
措置法通達69の4-21では、特定居住用宅地等の規定の「同居」していた者とは、当該家屋で被相続人と起居を共にしていたものをいい、共同住宅の場合は、同一の独立部分に居住していた場合に同居として取り扱われると規定している。
従って、上記の長男は、被相続人と同居していたとは言えず、小規模宅地の特例の適用はない。
事例⑤ 二世帯住宅の取扱い
相談内容:
被相続人とその長男は被相続人の所有する土地の上に、二世帯住宅を建て、一階部分を被相続人が所有、二階部分は長男が所有し、住んでいた。両者は別生計だった。
相続が開始し、長男は、建物の一階部分と土地を相続した。
配偶者はなく、同居していた他の親族もなかった。
この場合、敷地である土地について、特定居住用宅地として小規模宅地の特例の適用はあるか。
回答:
措置法通達69の4-21では、特定居住用宅地等の規定の「同居」していた者とは、当該家屋で被相続人と起居を共にしていたものをいい、共同住宅の場合は、同一の独立部分に居住していた場合に同居として取り扱われると規定しているが、なお書き部分で、次の要件を全て満たす場合には同居として取り扱われると規定してる。
- その建物の全部を被相続人又はその親族が所有していること。
- 相続人の配偶者又は被相続人の居住部分に同居の法定相続人がいないこと。
上記の長男の場合は、この二つの要件を満たすので、被相続人の同居の親族と認められ、小規模宅地の特例の適用がある。
二世帯住宅ではなく、長男が同じ敷地内に別棟を建てて住んでいる場合は、同居とは見なされないので、注意が必要である。(税務通信NO.3188 号)
事例⑥ 入院・老人ホームへの入所していた場合
相談内容:
被相続人が入院・老人ホームへ入所中に相続が開始した場合に、その相続人が入院・入所前に居住していた居宅の宅地が、特定居住用宅地と見なされるか。
回答:
入院の場合は、一時的なものであり、その居宅が他の用途に供されていた場合を除き、生活の拠点は入院前の居宅にあると考えられるので、入院期間の長短を問わず、その宅地は被相続人の居住の用に供されていたものと解される。
老人ホーム入所の場合は、一般的には生活の拠点を移転したものと解されますが、個々の事例の中には自宅へ戻りたいと望みながら、介護等を受けるため止む無く入所しており、自宅はいつでも戻れるように維持管理している場合もあり、一律に判断することは困難である。
次の要件を満たしている場合は、自宅は被相続人の居住の用に供されていたと解することができると思われる。
- 介護等を受ける必要があるため、老人ホームに入所することとなったと認められること。(特別養護老人ホームの場合はこの要件を満たすと考えられる。)
- 自宅は、被相続人がいつでも生活できるように維持管理されていたこと。
- 入所後、新たにその建物を他の者の居住用その他の用に供していた事実がないこと。
- その老人ホームは所有権又は終身利用権を取得して入所したものではないこと。
小池正明先生「相続税小規模宅地特例の実務」
戻る
![[[三人寄れば文殊の知恵>文殊の説明]] [[三人寄れば文殊の知恵>文殊の説明]]](swfu/d/a_ilst006.gif)