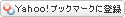2016-02-16 理事長に対する貸付金の利息相当額の評価
2016-02-16 理事長に対する貸付金の利息相当額の評価
JUSTAX NO.271 2016年2月
理事長に対する貸付金の利息相当額の評価
所得税基本通達36-49の合理性
法人が役員に対して、通常の利率より低い利率で金銭の貸付けをした場合、通常の利息相当額と役員が負担した利息額との差額は経済的利益の額として、役員の給与等の収入金額とされます。今回は、医療法人の
理事長に対する貸付金について、その利息相当額の評価について争われた判決をご紹介します。
(平成27年5月26日東京地裁・棄却l・控訴・TAINSコードZ888-1961)
く事案の概要>
この事案は、A社(医療法人)の理事長を務める原告が、平成20年分ないし平成22年分の所得税の確定申告をしたところ、処分行政庁が、A社に係る法人税の調査に基づき、原告がA社から借り入れた金員(本件借入金、債権者であるA社においては本件貸付金)に係る支払利息について、本件借入金に対し通常支払うべき利息の額(本件利息相当額)とA社が決算において収入に計上した利息の額との差額相当額が原告に対する経済的利益の供与と認められるとして、各年分の所得税について、その経済的利益の額を給与所得』こ加算し更正処分等を行ったことから、原告がその取消しを求めたものてす。
く裁判所の判断>
東京地裁では、次のとおり、本件利息相当額の算定について、所得税基本通達36-49((利息相当額の評価》後段の定める利率によることが相当であると判断し、原告の請求を斥けました。
① 原告は、未払給与等債務額と本件貸付金とが相殺されるべきである旨主張するが、未払給与等債務額と本件貸付金については、実際に相殺等の経理処理が行われるまでの聞は、原告とA社との伺の債権債務として別個独立して存在するものとみるのが相当であるし、原告は、未払給与等債務額と本件貸付金に関する原告とA社との聞の事前の相殺合意についても何ら主張立証をしていなし、から、原告の主張は採用できない。
②使用者が役員または使用人に貸し付けた金銭の利息相当額の評価について、所得税基本通達36-49は「当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の利率を加算した利率(括弧内省略)により評価する。Jと定めている(注平成25年課法9ー7による改正前) 。
③本件において、A社が本件貸付金に付した利率は、O.01%ないし2.0%とされているところ、これらの利率が、A社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率の定めによったものと認められるような事情はうかがわれないから、所得税基本通達36-28((課税しない経済的利益》
(2) の「課税しなくて差し支えなし、」との取扱いを採用することはできず、本件貸付金の利息棉当額の評価に当たり適用される利率は、商業手形の基準割引率に年4%を加算した4.1 %ないし4.5%を採用するのが妥当である。
③ 使用者が役員等に貸し付けた金銭が、使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかではない場合に、利息相当額を個別に評価することとすると、貸主と借主の関係、担保の有無とその種類、貸付期間など種々の要素により異なった評価額が生じることとなり、納税者の予測可能性を害する上、課税事務の統一的な執行が困難になるおそれを生じさせるから、客観性を有する基準によって画一的に評価するという所得税基本通達36-49の定めは、納税者の予測可能性の向上、納税者間の公平、納税者の便宜及ひ徴税費用の節減という見地から見て合理的なものというべきである。
]USTAX第271号{平成28年2月10日号)/編集・発行東京税理士会データ通信協同組合・広報部
干151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-9更生保護会館
/TEL(03)3350-6300FAX (03)3350-4628
![[[三人寄れば文殊の知恵>文殊の説明]] [[三人寄れば文殊の知恵>文殊の説明]]](swfu/d/a_ilst006.gif)